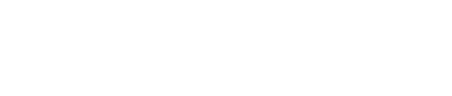高橋 信– Author –
-

広報とよおか連載開始
市広報に「生きものイキイキ観察記」という連載コラムを、コウノトリ市民研究所が... -

田んぼの学校2014年4月度
タンポポ探し、春の草を食べる 日時:2014年4月20日(日)9:30-12:00 天気:曇り ... -

豊岡盆地の冬鳥観察会
日時:2014年2月9日 9:30~11:00 集合場所:コウノトリ文化館 観... -

アカガエルの卵塊初認
本日2月4日、コウノトリの郷公園内の西公開ビオトープにて、アカガエルの卵塊を... -

田んぼの学校1月度(2013.1.20)
実施日:2013年1月20日 参加人数:約20人 天気:曇り ちょうど第3回の企... -

生物多様性企画展開催中
県立コウノトリの郷公園内にある、豊岡市立コウノトリ文化館の玄関ホールにて、N... -

ホタル観察会
2012年6月20日(水)コウノトリの郷公園内で豊岡市主催のホタル観察会が開催されま... -

ビオトープの整備
GW初日は、観光客も少なく郷公園内は落ち着いた雰囲気。萌黄の里山が美しく、キ... -

田んぼの学校1月度
日 時:2012年1月15日(日)9:30~12:00 テーマ:里山観察、足跡や野鳥など、雪遊... -

田んぼの学校9月度 イナゴ、バッタ
2010年度田んぼの学校9月度 9月19日(日) あぜ道の生きもの、イナゴやバ...