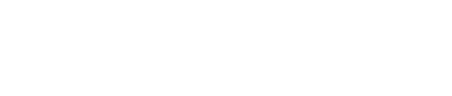▼Blog– category –
-

秋の鶴見茶屋
2025年11月3日(祝・月)10時~13時 秋の鶴見茶屋を開催しました。あいにくの時雨... -

キノコ・粘菌観察会2025年11月(実施報告)
キノコ・粘菌観察会令和7年11月2日13:00~15:00参加者16名 スタッフ1 アカイボ... -

コウノトリ放鳥20周年記念パネル展
企画展:コウノトリ放鳥20周年記念パネル展(兵庫県立コウノトリの郷公園)期間... -

文化館だより2025年11月号
文化館だより2025年11月号ダウンロード -

植物観察会2025年10月(実施報告)
日時:2025年10月26日(日)13:00〜15:00場所:神鍋山天気:晴れ参加者:3名スタッ... -

田んぼの学校2025年10月(実施報告)
2025年10月19日(日)9:30~11:00テーマ:アカトンボ探し参加者:10家族28名、スタッ... -

コウノトリ野鳥観察会2025年10月(実施報告)
日時:2025年10月12日(日)13:00〜14:30天気:くもり参加者:20名案内人:高橋 盛... -

キノコ・粘菌観察会2025年10月(実施報告)
キノコ・粘菌観察会令和7年10月5日13:00~15:00参加者19名 スタッフ2 今回の... -

植物観察会2025年9月(実施報告)
日時:2025年9月28日(日)9:30〜11:30場所:ハチゴロウの戸島湿地天気:晴れ参加... -

文化館だより2025年10月号
文化館だより2025年10月号ダウンロード