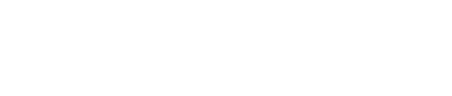▼Blog– category –
-

夏休み昆虫採集7月(実施報告)
2024年7月28日(日) 参加者22名 スタッフ2名 暑い中、元気よく出発。まず、アブ... -

コウノトリふれ愛コンサート♬
2024年7月20日(土) 真夏の夕べ、約150名が集い、素敵な時間を過ごしました。 毬... -

田んぼの学校2024年7月(実施報告)
2024年7月21日(日)9:30~11:00 テーマ:小川の生きもの探し 参加者:44名、スタッ... -

キノコ・粘菌観察会2024年7月(実施報告)
日時:2024年7月7日(日)9:30~12:00 天気:晴れ 参加者:10名 スタッフ:2名 参... -

植物観察会2024年6月(実施報告)
日時:2024年6月23日(日)13:00〜15:00 天気:雨 参加者:2名 スタッフ:2名 天気... -

田んぼの学校2024年6月(実施報告)
2024年6月16日(日)9:30~11:00 テーマ:初夏のビオトープ 参加者:37名、スタッフ6... -

コウノトリ野鳥観察会2024年6月度(実施報告)
日時:2024年6月9日(日)9:30〜11:30 天気:雨 参加者:8名(3組) 案内人:高橋... -

ホタル観察会
2024年6月7日(金)20時~21時 今年はホタルが舞うのは遅いのではないかと心配して... -

キノコ・粘菌観察会2024年6月
2024年6月2日13:00~15:00 参加者11名 スタッフ2 お昼前に雨が降り、... -

春の鶴見茶屋
5月26日「春の鶴見茶屋」を限定開店しました。 祥雲寺巣塔のコウノトリの様子が目...