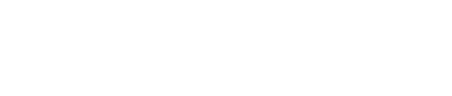▼活動レポート– category –
-

山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク再認証審査
山陰海岸ジオパークの世界審査の最終日、その最後の審査サイトがコウノトリ文化館... -

コウノトリふれ愛コンサート2018【実施報告】
開催日時:2018年8月5日(日)17:30〜19:00 来場者:150名 天... -

里山の昆虫採集(実施報告)
日時:2018年7月28日(土)9時半~12時参加者:5名(2家族)+スタッ... -

菅村先生の植物観察会7月度(実施報告)
テーマ:夏の植物 ネジバナ、アキノエノコログサなど日時:2018年7月22日(日... -

菅村先生の植物観察会6月度(実施報告)
テーマ:夏の植物 ニワゼキショウ、ヒナギキョウなど日時:2018年6月25日(日)13... -

ホタルのゆうべ2018(実施報告)
日時:2018年6月15日(金)19時30分~21時場所:コウノトリ文化館~... -

コウノトリ自然観察会6月度(実施報告)
テーマ:巣立ちコウノトリと野山の鳥日時:2018年6月10日(日)13:00〜15:30天... -

菅村先生の植物観察会5月度(実施報告)
テーマ:春の植物 ニワゼキショウ、ヘビイチゴなど日時:2018年5月27日(日)1... -

春の鶴見茶屋2018(実施報告)
日時:2018年5月27日(日)10:00~15:00 場所:文化館和室およびその周辺 参加人数... -

コウノトリ自然観察会5月度(実施報告)
テーマ:コウノトリのヒナと夏鳥日時:2018年5月13日(日)13:00〜16:00天気:...